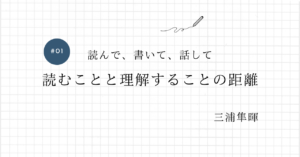当塾で講師兼アドバイザーを務める佐藤宗大さんより、研究内容の紹介文を寄稿していただきました。

佐藤 宗大(アドバイザー)
Profile
京都大学大学院文学研究科西洋哲学史専修修了。修士(文学)。「哲学を社会の力に」との思いから、教育系ベンチャーに就職ののち独立し、個人事務所OFFICE Kを設立。国語を中心に、多くの生徒を志望校へと導く。現在は「哲学×国語教育」をテーマに、日本有数の教育研究拠点である広島大学で研究活動中。アースリードの指導方法に対して、専門的見地から助言を行う。
むかし、まだ哲学史の院生だったころ。当時の先輩に誘われて、倫理学の勉強会に参加していた。英語文献の読書会で、ろくすっぽ質問もできないまま修論執筆を言い訳に幽霊化していったのだけれど、そういうのに限って本題と関係ないことばかりが頭に残っていたりする。
ある日の研究会の雑談で、海外の大御所の話がネタになった。その先生は(検閲削除)で、その現場を見られてのたまったことには、「自分が倫理の外に立たなければ、倫理について考えることなんてできはしない」、と。
当然こんな与太話は半分以上フィクションだとは思うが(そうでなければたまったものではない)、この大御所の言葉が、妙に自分の中で残り続けている。とっさの一言にしては、ずいぶんと本質をついているように感じるからだ。
国語といえば「言葉」に関する学習をするものだ、ということを疑う人は誰もいないだろう。『小学校学習指導要領(平成29年告示)』にも、国語化の目標は「言葉による見方・考え方を働かせ,言語活動を通して,国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を……育成することを目指す」(文部科学省 2018 p.28)ことだとバッチリ書いてある。だから私たちは国語の時間で漢字を習い、文章を書き、話し合いの仕方を学び、そしていろいろな文章を読む。
私の専門である国語教育(学)が対象にするのは、この「言葉」の学びとはどのようなものでありうるのかということだ。国語の時間でどのようなことが扱われなくてはならないか、そしてそれをどのように「面白く」授業にするか。いま国語教育(学)は、「言葉」の学びのあり方そのもの、いやそもそも「言葉」とは何かを問い直す局面に立っているとも言える。たとえば、近年では国語科で扱うべき知識・技能として、「情報の扱い方」に関する事項が増えた。そのため、グラフなどはもちろん、動画コンテンツなども当然のように国語の授業の素材となっている。文字で書かれたものを読み書きすることをベースにしていては、もう国語の授業なんてできない時代なのだ。
そうなったときに、自分には、例の大御所の言葉がふと思い出されるのだ。
国語教育について考えようとするのなら、私(たち)は「言葉」の外に立たなければならないのではないか?しかし、立てているんだろうか?そもそも、「言葉」の「外」ってなんなんだ??
国語教育学というのは、学問としてまだまだ若い。出発点をどこにするかにはいろいろな議論があるけれど、たとえば、哲学とか数学とか、そうした「老舗」に比べたらつい最近できたようなものと言っていい。だから、自分たちが問題だと思ったり課題だと感じたことを、さまざまな理論や言葉、そして「先生」としての実感から出た言葉などを柔軟に用いながら表現してきた。
柔軟というと聞こえはいいが、そこに学問としての国語教育学をめぐる深刻な問題がある(んじゃないかなあとぼんやり思っている)。
国語教育では、自分たちが考えようとする問題を記述するために、関連する学問領域の言葉や枠組みを参照するということがよくある。たとえば、文学研究理論だとか言語学とか、「言葉」に関わる学問である。しかし、どうしたって本職は国語教育だから、文学研究なり言語学なりが精密に分かるとも限らない。あくまで描きたいのは目の前の国語教育の問題だから、よその議論が結果的に「道具」として位置づきやすいことも事実である。そして、「国語」なんだから自分たちが問題にしているのは具体的な「言葉」の仕組みや性質だろうという意識も根強い。
と、なるとである。国語教育は、具体的な「言葉」の仕組みや性質を問題にしようとする意識に基づいて、「言葉」に関わる議論を形式的に援用しているんじゃないかという可能性が出てくる。そのとき、国語教育は結果的には「言葉」の内側にとどまっているのではないだろうか?もしそうだとしたら、私たちは「国語」の授業について考えていたとしても、「国語教育」について考えられているんだろうか……そんな残酷なことを思ってしまう。
もちろん、議論している当人にはそんなつもりはないだろうし、私自身含め、みんな「国語教育」について考えようとしているのは間違いない。ただ、人は「言葉」に左右されるから、いつの間にか借りてきた「言葉」に表現しようとしたメッセージが乗っ取られるということもあるだろう。それに、生きて動く教育や子どもの問題を描くのに、「外」に出て眺めるなどという悠長なことをしていられないのも事実だ。「言葉」の教育である国語教育にとって、「言葉」の「外」に立つというのはいろいろな意味で難しいのである。
カント哲学という「外」の世界からやってきた私だから見えてくるものもあるんじゃないだろうか。そんなことを思いながら、日々研究を続けている。
国語教育がずっと扱ってきていながらなかなか扱いに困っているものに、「言葉にならない何か」がある。文学作品を読むというような状況に限らず、普段の生活でさえ、「うまく言えない」というような体験はよくあるだろう。そういった場面のいくつかは、表現能力とか語彙とかのレベルアップでカバーできるかもしれない。でも、表現能力や語彙を伸ばしていけば、どんなことでも言語化できるんだろうか?そもそも、「言葉」の学びとは、「言葉にならない何か」を「言葉」に表しきるということなんだろうか?
「言葉」とは本性的に「ボキャ貧」なのだ、と私は思っている。だからこそ「言葉」になったものを受け取るためには、その背後にある「伝えようとしたこと」をも捉えようとしなければならない。また、「言葉」の能力や知識を上げていったとて、全ての「言葉」が理解できるわけでもないし、全てを「言葉」で表現しきれるわけでもない。それはかえって、「言葉」によって伝えようとするものを、「言葉」で伝えきれる範囲に押しとどめてしまいかねない。
だから、「言葉」の学びには、「言葉にならない何か」が必要なのだ。そして、それを「言葉」にしようとするのではなく、むしろ「言葉」にできないということを積極的に受け止めていかなくてはならない。しかし、「言葉」の学びに「言葉にならない何か」を位置付けるというのは実に矛盾した課題でもある。少なくとも、国語教育の内部には、それを描ききるだけの「言葉」は十分に存在しない。
そこで哲学の登場である。哲学の話法というのは、言われたこと・書かれたことをデコードするのにやや手間がかかるが(1フレーズごとに重めのZIPファイルが仕込まれているようなもんだろうか)、「言葉にならない何か」を扱うことには向いているなあと感じる。たとえば、カントの「物自体(Ding an sich)」概念は、私たちの経験の向こうにある「何か」を記述する一つの方法だとも言える。この哲学の話法や視点を、国語教育の問題圏と接続できないか。それが私の今の研究である。
ただ、当然ながら、哲学と国語教育とでは「言葉」も学問の作法も違う。哲学のやり方で論じれば通じるというものでもないし、国語教育の流儀で研究活動をする中で「これでいいのか?」と慣れなさを感じることもある。しかし、それがうまく結合できなければ、自分の研究にとっても国語教育にとっても意味はないんだろうなとも感じる。先日、千葉で行われた全国学会で、はじめて小学校での授業実践を報告するタイプの発表を行った。これまではカントをベースに理論寄りの話をすることが多かったから、カントなしで実際の授業や子どもたちのことを話すなんて……と準備しながら不安の大きい学会だった。しかし、結果的には現職の先生や現場経験のある研究者の方から質問や好意的な意見をたくさんいただけて、少しは自分のなすべきことに近づいてこれただろうか、なんて思っている。
「外」から眺めつつ、しっかりと「中」にある切実な問題とも接続していく。そんな研究者にいつかなれたらいいいなと思いつつ、博士論文の執筆がなかなか進まない今日この頃である。