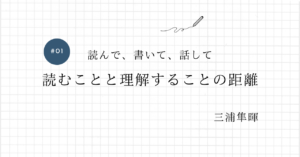当塾で講師兼アドバイザーを務める佐藤宗大さんより、国語教育についてのコラムを寄稿していただきました。本コラムでは、哲学と国語教育の未来について、専門家の立場から考察していただいています。

佐藤 宗大(アドバイザー)
Profile
京都大学大学院文学研究科西洋哲学史専修修了。修士(文学)。「哲学を社会の力に」との思いから、教育系ベンチャーに就職ののち独立し、個人事務所OFFICE Kを設立。国語を中心に、多くの生徒を志望校へと導く。現在は「哲学×国語教育」をテーマに、日本有数の教育研究拠点である広島大学で研究活動中。アースリードの指導方法に対して、専門的見地から助言を行う。
哲学と教育との深い関係
哲学もずいぶん愛想がいい学問になったなあ、と感じることが多くなった。「世間と隔絶しひたすら思索に耽る」なんてイメージはとっくに時代遅れだ。大都市では街角のカフェで哲学対話のイベントが開かれていたり、あるいは企業のコンサルタントに哲学が関わっていたりする、という噂を耳にする。あまりやりすぎると「若者をたぶらかした」と死刑を宣告される羽目になるが(数千年前のアテナイという街にそういう人がいた。名をソクラテスという)、哲学は社会とつながっているし、私たちの生活の中にしれっと存在している。そんな世の中になりつつある。
そうした哲学と社会とのつながりの一つが「教育」だ。そもそも元をたどれば、教育と哲学とは兄弟のようなものだった。むしろ私などは、哲学が目指す世界や社会を具体的に実現していこうとする営みの一つが教育なのだ、と考えている。証拠というわけではないが、哲学者の中には、教育の方面でもその名がよく知られている人が何人もいる。たとえば、ルソーの『エミール』といえば教育学の古典中の古典だし、プラグマティズムの巨人デューイは、アメリカの教育学理論や、その影響を強く受けている日本の戦後教育を考える上で避けては通れない存在だ。こういうわけで、哲学と教育とは、学問レベルですでに密接な関わりがある。
哲学と教育とのビミョーな関係
とはいえ、哲学と教育とは同じではない(当たり前だ)。このへんは「学的アイデンティティ」とか「学問のアクチュアリティ」とか、いろいろ根深いというかめんどくさいというか、要はこの紙幅では触れられない問題があるのだが、まあそれはいい。シンプルに両者の関係について一番ネックなのは、それぞれが対象としている人間モデルの違いだ。
どういうことか。哲学が議論の対象にしているものは、それが「主体」であれ「社会」であれ「芸術」であれ、無意識に「大人」の世界であることが多い。しかし、教育(学)が取り組んでいるのは「子ども」の成長である(もちろん高等教育とか成人教育とかもあるが、それはとりあえず置いておく)。またまた当たり前の話だが、「大人」と「子ども」とは違う。したがって、「大人」の理性をベースにした哲学の理論や発想を、「子ども」の成長や発達に関してそのまま当てはめるわけにはいかない。乱暴に言えば、ここが哲学と教育(学)との分岐点である。先ほど名前の上がったルソーやデューイは、そもそもの関心に「子ども」が含まれていればこそ、教育(学)でも重要な役割を果たしている、と言えるのかもしれない。
つまり、「大人」の世界に哲学を売り込むことほど、教育に哲学をつなげていくことは簡単ではない。いや、「大人」が本当に哲学の想定するような「大人」なのか?と疑ってみると、実は「大人」たちにすら、哲学をつなげていくのは容易ではないのかもしれない。となると、ますます哲学は教育と手を携えていなかければいけない。ここで話は出発点に戻る。
さてさて、どうしたらいいのだろうか?
哲学と教育とのこれからの関係(?)
哲学と教育とを結びつける方法は、今のところ大きく2つある。
まずひとつは、哲学自体を教育すること。つまりは「哲学教育」である。最近は日本でも「子どものための哲学(Philosophy for Children, 通称P4C)」に関する研究や実践事例が増えてきており、Eテレでも研究者の監修のもと、「Q 〜こどものための哲学」という番組が制作されたりしている。すごい時代になったもんだ。
それからもうひとつは、教育という営みに哲学がパートナーとしてコミットしていくこと。つまり、哲学を学ばせるのではなく、「学ぶ」こと自体を哲学の立場から一緒に考えて、具体的な「学び」につなげていこうということだ。
前者のアプローチのほうが日本では目新しいが、私が研究者として、哲学と教育とをクロスオーバーさせために取り組んでいるのは後者のやり方である。
いま、国語教育には、何としてでも哲学が必要だ。それは、近頃はやりの「ロジカルシンキング」に関してだけではない。国語教育が育てるべき「リテラシー」の把握と具体化にあたって、哲学が大きな役割を果たすと考えている。
今の小学生にとって、「読む」対象は「文章」だけではない。チラシや絵、あるいはグラフなど、目に入る「情報」そのものすべてが「読む」ことのうちに含まれている。そして、「読み」の妥当性は、飛び込んでくる「情報」を自分がどう受け取り、根拠づけるかによって測られる。こうした「情報」との接し方や態度・能力を、幅広く「リテラシー」という。「読む」と言ったら「文章」を読むのであって、「筆者の言いたいこと」を正確に読み取らなければならないというような時代は、とうに過去のものなのだ。
「わたし」に与えられてくる「情報」をどう根拠づけながら、「私」の「読み」として構成するのか。これはもはや、「ことば」を超えた「認識」をめぐる問題だと言っていい。いや、むしろ「ことば」の内側にとどまっていては、「ことば」以外の「情報」とどう向き合うのかは考えられない。だから、「ことば」にならないものや、「ことば」を超えたものを扱えるパートナーが、国語教育には必要だ。
ここで哲学が出ていかなくて、誰が出ていくというのだろうか。哲学の本領は「論理」だけではない。「考える」ことを足場に、あらゆるものを概念として取り扱おうとするその営みに、哲学の哲学らしさがあると私は考えている。だからこそ、国語教育の課題を、哲学もまた同じように課題として引き受け、一緒に考えていける。そう私は信じている。
では、哲学と国語教育がタッグを組むと、どんな授業ができあがるのか?それは、この会社も一つの可能性を示してくれるだろうし、何より私の研究の先にその答え(の一つ)がある。
というわけで、皆さん、近い未来にお会いしましょう。